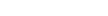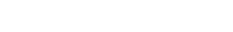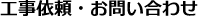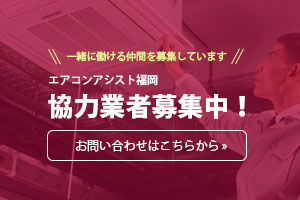通風と排熱の工夫①――――ヒートチムニー
2016年2月12日
台所のいろりの煙を屋根で抜く仕掛けです。煮炊きの上昇気流で屋根からエアコン排熱されていくのですが、出て行く空気があるということは入ってくる空気が必要ということ。そのためにも無双窓が必要です。風と熱の出入りと通路を考え、小さな工夫が積み上げられています。
通風と排熱の工夫②――――無双窓
台所などにみられる開閉できる換気口。特別な金物がいらない手軽な手法です。平均風速が5メートル、風のある地域ならではの有効な窓と思います。
木製デッキだって照り返しが暑い。
季節の良い日に室内とデッキが一体となる半戸外の気持ちよさ。エアコンしかし真夏では、たとえ木製のデッキでも、照り返しが強くなり、熱風の取り入れ口のようになってしまうこともあります。
遮熱にも最も有効なのは大屋根をかけることですが、空が見えないデッキでは、その魅力が半減してしまいます。この家では、デッキを所々欠き込んで樹木を植えました。
中央部にはデッキの遮熱を考えて落葉樹(シャラとカエデ)、和室前には濡れ緑を暖めず、隣の家からの視線を遮る樹緑葉(ソヨゴ)、ついでにデッキに段差をつけて庭のレベルに繋がるようにしました。寝転がったり、腰かけたり、屏にもたれかかったりと、気持ちの良い半戸外ができました。
南の下屋はヒーターになってしまう
まだ建築学生だった頃の話ですが、課題をチェックしてくれた教授が「南に下屋を付けると夏暑くて大変だよ」とアドバイスをくれました。造形ばかりを追い求めがちな学生時代、そのような話はほとんど「馬の耳に念仏。」
しかし実際にやっていると、エアコン南面に下屋をだした時の2階の厚さといったらありません。特に屋根の仕上げを黒色鉄板などにしていると大変です。
太陽に熱せられた下屋に面した部屋はまるで真夏にヒーターを足元に置いているようなもの、2階の窓を開けると熱風が入ってくることになります。